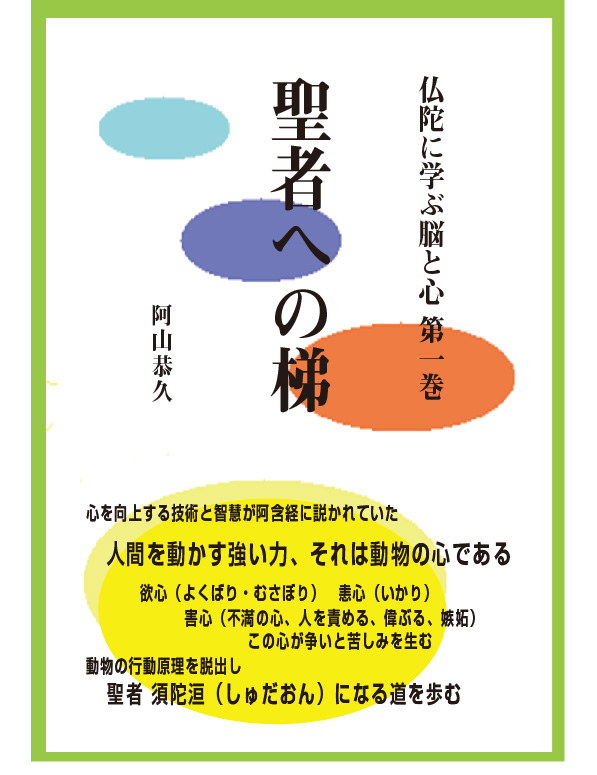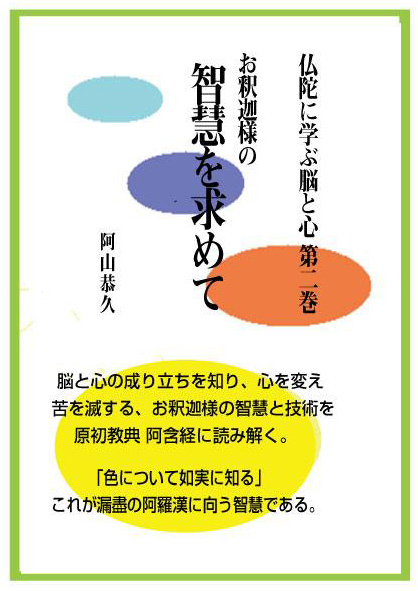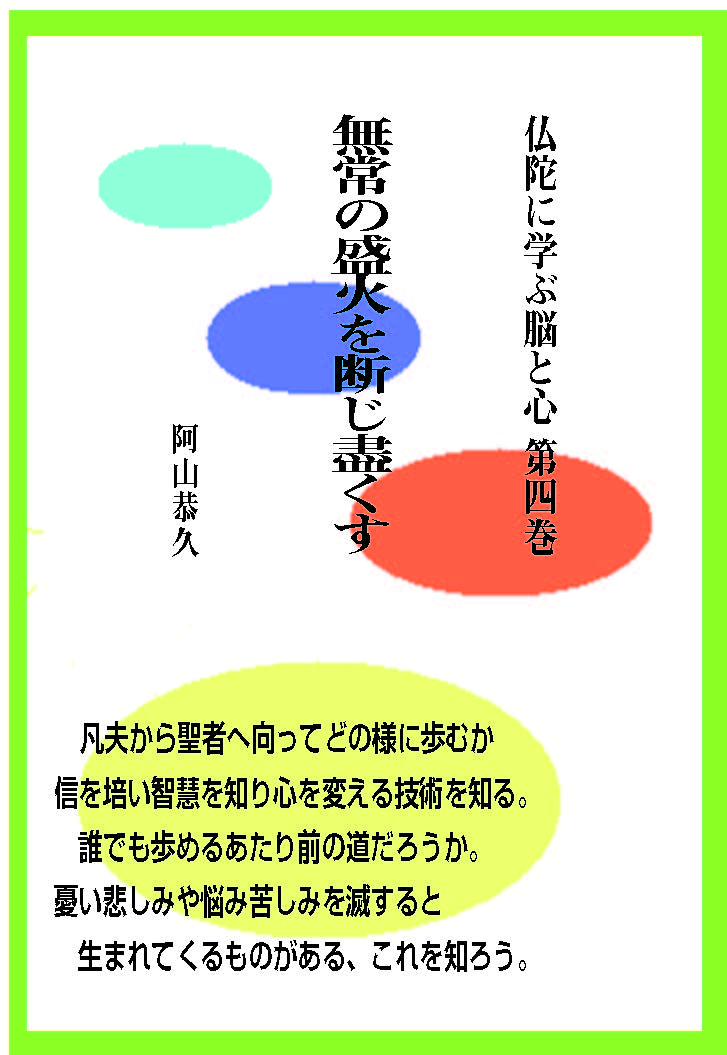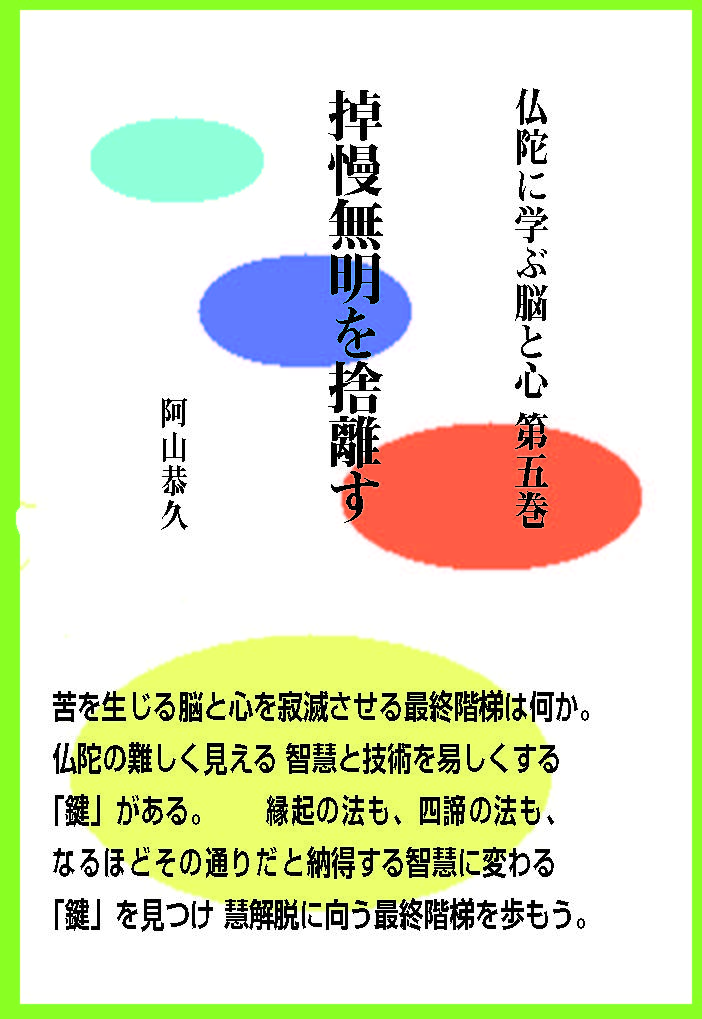在家の阿羅漢へ --施を為す
(己利を逮得す) 雑阿含経難提経より②
平成24年10月12日阿山恭久記す(平成29年5月24日改訂K.)
このページは多くの阿含経典の中で著者阿山恭久が最も大切な経典の一つであるとする「難提経」の後半部分を解説しています。
難提経の前半を解説した「歓喜を生ず」のページには、「常に五種の歓喜の處を修習す」べきことが説かれていました。「歓喜の處の修習」は、「佛・法・僧・戒・世」でした。
歓喜を修習して功徳を得ると、「己利を逮得」します。すなわち阿羅漢の実践が始まるのです。阿羅漢は「
五種の施」を実践します。このページでは阿羅漢に至った先達が修習する「
五種の施」が説かれます。お釈迦様のご指導に耳を傾けましょう。
(タイトル以外の太字の部分は 概ね 国訳一切経印度撰述の部阿含の部 大東出版社 から引用しています)
己利を得たり
時に随ひて憶念せよ
どんな時にもこのことを思い出して心を向けているようにしなさい。
『我れ己利を得たり。
私は五つの歓喜を修習ずることを実践して、己利を得たのです。
「己利を得たり」とは何か。五つの歓喜を実践して心の境涯が今までとは質の違うものになったのです。難提経では「己利を得たり」についてここから説かれています。
「己利を得たり」とは 、全ての願いが「施」に向かっているのです。
阿羅漢になったことを自分で分かる大切な感覚です。
凡夫の特徴である自分の利を求める心が全くなくなっている、すなわち阿羅漢の感覚で満たされています。
五種の施を為せ
我れ慳垢の衆生の所に於て 當に多く慳垢を離れて住することを修習し、
私は今は慳垢の衆生のなかで生活しています。衆生は働き慳しみをし、人の働きを貪り、自分だけの利のために心を動かし、物慳しみをし、懈怠を為す汚れた心をもった人達です。
この様な人々の中で私は慳垢の心を離れて生活することを修習しており、(慳垢の心 人に対して親切に出来ない汚れた心)
解脱施、捨施、常熾然施を修し、
捨の平等惠施を楽い
常に施の心を懐くべし』と。解脱施を修し、捨施を修し、常熾然施を修して、
捨の平等惠施を祈念し、
常に施の心を懐いていよう』と。施(ほどこし)をするというと、自分が立場が上で、徳のない人に物を与えるという感覚になりがちです。
しかし、ここでの施は少し違う心の向きが求められています。
もちろん人に施を為すには、自分が施すものを持ち合わせていることが必要です。誰でも持っていないものを施すことは出来ません。もし自分が持っていないものであったら、これを施すには先ず自分の中に作り上げなければなりません。施の修行はここから始まります。
けれども、たとえいくら自分が沢山持っているものであっても慳しむ気持ちがあって、自己中心の心が動いていると、 まず自分の利と子孫や一族の利が大切になって人に施すことはなかなか出来ないものです。
お釈迦様は私達に「苦から脱出する」方法を説いて下さっているのでした。 「苦から脱出する」方法は、五種の歓喜を修習することでした。自分の悪い心癖を出さずに、世の中に役に立っていれば、歓喜を生じるのです。 でも、これだけでは自己中心の心から脱した、高い境涯に到達したとはいえません。
解脱を成就した阿羅漢の境涯では「梵行已に立ち」という生活が出来るようになります。 凡夫の心と行動の原点は自分の利を求めることです。 聖者である阿羅漢は、全ての時間の心と行動が、周囲の人々が苦しみのない幸せな生活をなせるように向いているのです。
これが「梵行已に立ち」である「施の実践」です。難提経では慳垢の衆生の中にいる在家であっても五つの施を修習せよと説かれています。
解脱施 愛(タンハー)の滅盡 - 漏盡解脱へ
一番目の施は解脱施です。 衆生の解脱が成就するように導くのです。
ここでの解脱は愛(タンハー)の滅盡を 指しています。
愛(タンハー)の滅盡は、四念処観によって「心は無常なり」が寂滅すると成就します。
前世で満たされなかった思いは今生に持ち込まれて、心の奥底に有結となって存在しています。 有結の思いをどうしても成し遂げたい、この心のエネルギーを愛(タンハー)と言います。 この愛(タンハー)のエネルギーがストレス感となって表面意識に漏れてくる、この漏を滅盡する有の漏盡解脱を為します。有の漏盡解脱は愛(タンハー)を滅盡するのです。
有の漏盡解脱を成就すると阿那含に到達します。(阿含経典には「愛(タンハー)」から生じる「有の有漏」の他に「欲の有漏」、「無明の有漏」が説かれています。この三つの漏については「仏陀に学ぶ脳と心」をご参照下さい。)
解脱施は、有結から生じる愛(タンハー)を滅盡します、このことを衆生に布施するのです。衆生の心に解脱を建立します。
捨施 我(が)と、愛(タンハー)への執着を捨てる
二番目の施は捨施です。
阿羅漢は「捨」の心が完成しているのです。捨には二つの捨があります。
動物の欲の無明と掉慢無明を捨離します。
動物の欲の無明によって、いわゆる「我(が)」が生じてきます。自分は偉いと思い、自分は正しいと主張し、自分を偉く見せよう執着するのです。
「捨」の第一は「我(が)」への執着を捨て離れます。
「捨」の第二は、愛(タンハー)の実現に執着する心の動きをなくします。いわゆる掉慢無明を捨離します。法次法向(色に於て厭を生じ、欲を離れ、滅盡に向う)によって捨が完成しま す。 また 四念処観の「法は無我なり」を成就しています。
心の解脱の作業は捨から出発すると見ることも出来ますが、心の三つの世界全てで散乱した部分が無くなって、最後に取り組むのも捨です。
この捨の心を布施します。衆生の心に捨を建立するのです。
常熾然施 あふれるような慈愛のエネルギーを施す
三番目の施は常熾然施です。
解脱を成就すると、勢いある強いエネルギーが生じてきます。この「常熾然」のエネルギーは、あふれるような慈愛のエネルギーです。 阿羅漢の行動力も成就力も慈愛のエネルギーから生じてきます。
慈愛のエネルギーによって、心に生じる様々な問題を解決し、為すべき事を成し遂げてゆく、 常に元気にあふれた燃えるような成就する力を生じています。この慈愛のエネルギーを周囲の人々の心に建立します。
「熾然」とは抜群の実践行動力をともなっていて、心に炎が燃えるような勢いがあることです。
「字通」を引くと「然」の文字は犬の脂を勢いよく火で燃やしている形を表していると言います。下にある四つの点々は火を表しています。 「熾然」の二つの文字ともに勢いよく燃え上がる火を表しているのです。
常熾然施は衆生の心に「常熾然」を建立します。
ここで一つ注意していなければならないことがあります。この勢いとエネルギーは怒りや不満のエネルギーではありません。自己主張のエネルギーでもありません。人を責め傷つける勢いであってはならないのです。勢いの種類を間違えないようにせねばなりません。
もう一度。
「常熾然」のエネルギーは、あふれるような慈愛のエネルギーです。ここまでの三つの施は「修せよ」という。すなわち施を実践せよと説かれています。 施の実践には修行者自身がこの境涯を成就していなければなりません。
捨の平等惠施
四番目の施は捨の平等惠施です。
捨を成就すると心が平等になります。この平等の心をプレゼント(恵)するのです。 人々の心に捨の成就と平等を建立します。
平等とは平らに等しい、すなわち心が平安で静かで、散乱した部分が無く、風がないときの湖の水面のようになっています。 心の解脱を成し遂げているのです。
平等惠 とは、この平等に到達している心のエネルギーを周囲の人々に及ぼして穏やかで安らかな空間を作り出します。さらに、周囲の人々の心に捨を実現し平等を建立します。
これが常熾然を為し遂げた聖弟子が向かう次の段階です。また聖弟子はこのエネルギーを、周りにやって来た「怨家」にもプレゼント出来るようになります。 怨家とは怨念のエネルギーを発している霊魂です。
「常熾然施」と「捨の平等惠施」によって、周りにいる霊魂が発している怨念のエネルギーを消滅させるのです。
なぜ、この様なことが言えるのか。
中阿含経分別六界経のテキストに「第一正惠施」という概念があります。「捨の平等惠」は乱れている怨家の心を寂滅すると説かれているのです。
「常熾然」と「捨の平等惠」は聖弟子の周りに暖かく穏やかで安らかな空間を作り出します。この空間によって、もし霊魂が怨念を生じていても穏やかになり怨念が消滅してゆきます。
周囲の人達もこのように為せるように楽(ねが)います。 「捨の平等惠施」は「修し」ではなく「楽い(ねがい)」と説かれています。 「捨の平等惠」を周囲の人々に建立するというよりも、施 を受けた人々がそのようになるのを願うのです。
常に施の心を懐くべし
五番目の施は「常に施の心を懐くべし」という。
ここまで四つの項目
解脱施、
捨施、
常熾然施、
捨の平等惠施を解脱の最終段階に向けて成し遂げてきました。
最後の段階はこの施の心を常に懐いていなさいという。
「常に 」というのはなかなか難しいのです。これが聖弟子に求められている 最終段階です。
毎日、常に施の心を働かせていることを求めています。施にも様々な形があります。
凡夫にも実践しやすい施に「無財の七施」(眼施・和顔施・和語施・身施・心施・床座施.房舎施)があります。
「無財の七施」は誰にでも実践出来る施の出発点です。そして一番勝れた施は「法施」すなわちこの経典に説かれている四つの施であると説かれています。
どのような施であっても、いつも周囲の人達の幸せを願って心を動かしているのです。
施の三昧へ
最初の四つの施は、解脱に向う衆生にとって必ず必要となるもの。 この四種の法施を施して周囲の人々が阿羅漢に向うように為します。
まさに無上の施というべきであると思います。そして五番目に常に施の心を懐くべし
とあります。一日中、常に施の心を持ち続けていなければなりません。
妻子がいても実践せよ
是の如く釋氏難提、此の五支の定、
若しは住、若しは行、若しは座、若しは臥、
乃至妻子倶ふも常に當に心を此の三昧の念に繋ぐべし』。このように釋氏難提よ、この五つの解脱に向う定(じょう 三昧に入った状態)を、じっとしているときも、動いているときも、坐っているときも、寝ているときも、また妻子がいて倶にいるときも、どんな時であっても常に心をこの三昧に向けて繋いでいなければなりません。
(三昧に向ける 常に施の心をいっぱいに満たして忘れることがないようにする)
五支の定とは何であったか。
①解脱施を修し、
②捨施を修し、
③常熾然施を修し、
④捨の平等惠施を楽い
⑤常に施の心を懐くこの五つの実践を為して、在家であっても常に心を施の三昧に繋いで過ごすのです。このように為せという。
まとめ
難提は妻子と一緒に過ごしている在家でありました。
妻子倶ふも、というのは在家であってもと言うことです。
何とも素晴らしいお釈迦様のご指導ではありませんか。在家であっても阿羅漢となって阿羅漢の修行を為せというのです。
これらの施を為すためには、まず自分がこのことを成就していて、心に確立していなければなりません。
私達も、今はまだ心が完成していなくても、ここに説かれていることが阿羅漢に向う道であることを知って実践できるのです。 心踊るお釈迦様の説法を感じて頂けたでしょうか。現代のこの難しい世の中では、どうしても元気が出なくて、恐れや不満を懐いて過ごしがちです。
このままの心では世の中を変えるのが難しいとは思われませんか。 この時こそ元気にあふれた勢いのある行動力と実践力が求められているのです。
お釈迦様はこの時代に合わせて、仏陀の智慧と技術が世の中に出て行くことをお見通しになって、この経典を伝えて下さいました。
私達はここに説かれた強く勢いのある「常熾然」と「捨の平等惠」を身につけて、必ずや新しい幸せな世界を切り拓いて行きたいものです。佛此の經を説き已り給ひしに、釋氏難提佛の説かせ給ふ所を聞きて、歡喜し隨喜し、禮を作して去りぬ。
雑阿含経 12633 難堤経より
釋氏難提はお釈迦様がお説きになったことを聞いて、歡喜し隨喜し、禮を作して去りました。
釋氏難提は歡喜し隨喜したという。通常の経典では歡喜だけなのです。歡喜し隨喜しという。
どんなに釋氏難提がこの説法に感激したかが伝わってくるようです。難提経おわり
本ページ先頭へ
歓喜を生ず へ 阿含経を読むTOPへ
ひの出版室HOMEへ
Copyright © 2012-2017 Web Design Thinknet,Japan Ltd All Rights Reserved.

160121 160307 160501 160514 160522 170520 170524