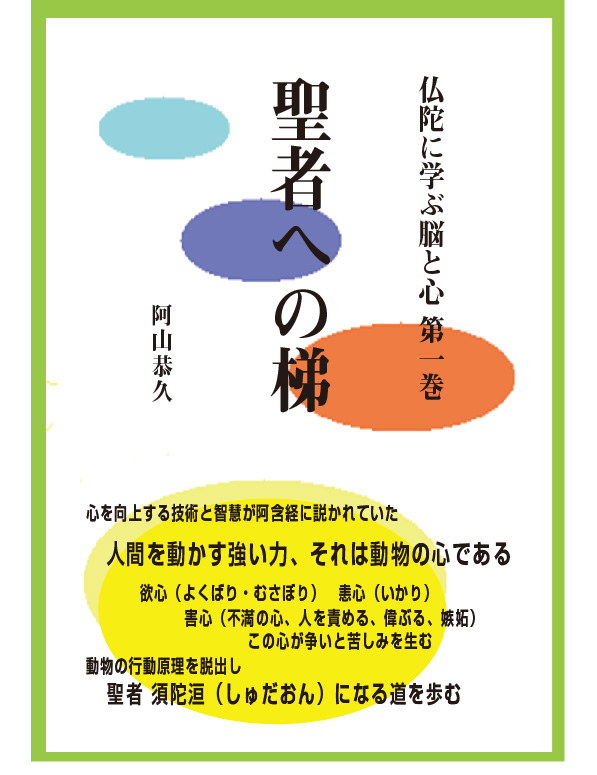
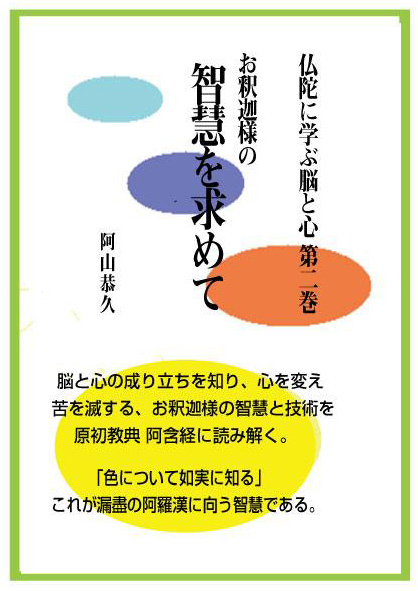

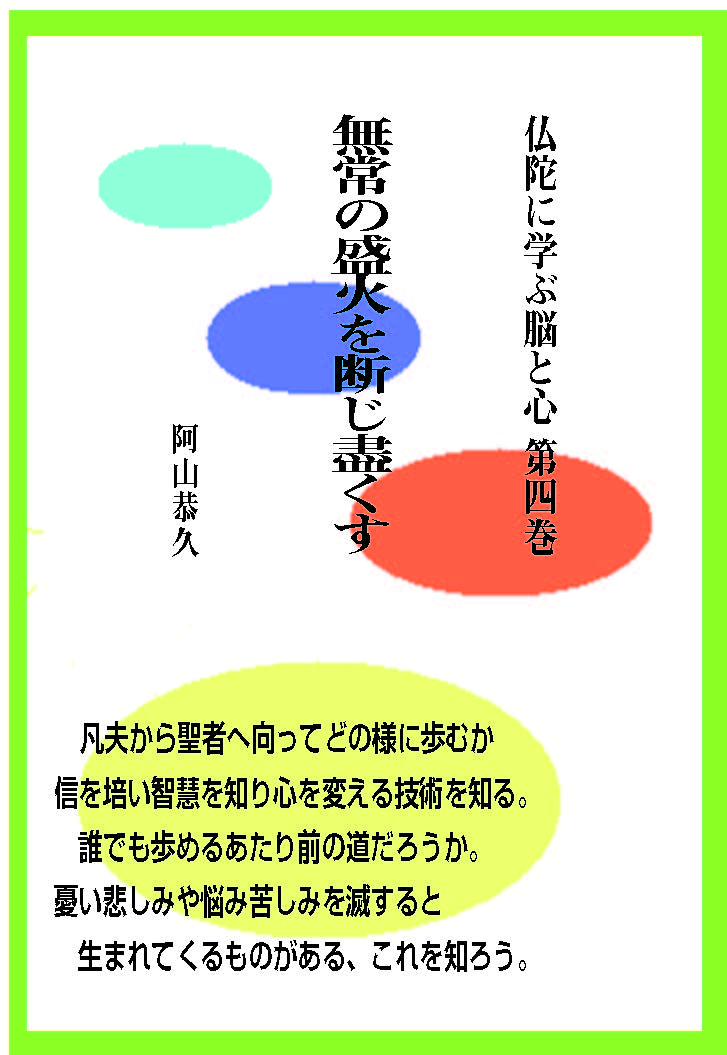
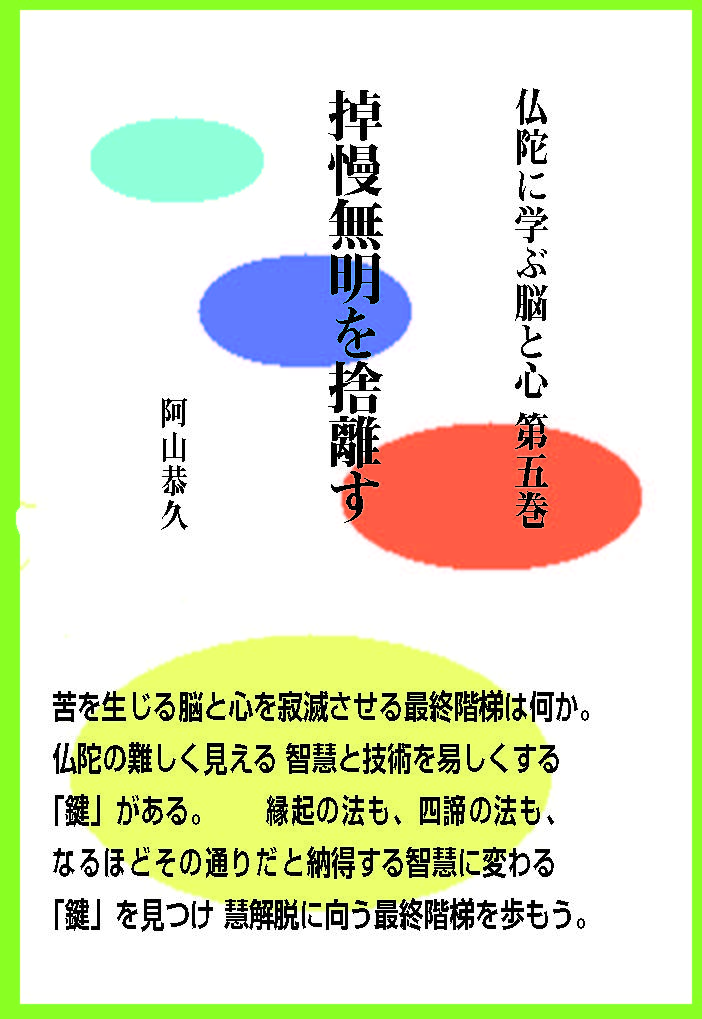
在家の解脱法 一切事経 ひの出版室
在家の解脱法 一切事経より
(聞・持・観・法次法向)
雑阿含経 一切事経より
平成27年5月15日 阿山恭久 記す
雑阿含経 一切事経は、雑阿含経 難提経とともに、優婆塞(在家の解脱に向かう修行者)が取り組むべき究極の解脱システムを示しています。この 二つの経典は一見異なる概念を説いているように見えますが、ともに「信戒施」の実践による解脱に向かう出発点から始まって、阿羅漢の「梵行已に立ち」の境涯までを示した、完成された解脱法とみることが出来ます。
このことを理解するには、本ホームページの「解脱に向かう」の中に示されている「信行」と「法行」における「忍を観察する」ことを理解し、同じく本ホームページによって「四念処観」による心の動かし方を知っておくことが役に立つと思います。
それでは一切事経の解説に入りましょう。
信戒施の実践
一切事経の先頭の部分に説かれているのは、信戒施の実践です。
信戒施の実践については、本ホームページ「歓喜を生ず」の項目の中で解説しております。このページは雑阿含経 難提経の基づいて解説したものですが、一切事経における信戒施も同様に解釈することができます。ご参照下さい。。
聞持観
一切事経の信戒施に続く題目は「聞持観」です。
経典には信戒施と聞持観との間には僧の所に訪問し先達とまみえるという「見」の段階が示されています。
何故、信戒施のつぎに聞持観が説かれているのでしょうか。聞持観が先にあって、その次に信戒施が来るのが自然であるとは思われませんか。
最初はお釈迦様への信(如来の十号に示されたお力を信じる)によって信戒施を実践し戒を護ります。いわゆる信行です。修行が進んで法行の段階になると奥深くにある心の動きを変える段階がやって来ます。戒の実践には、一乗道と言われている四念処観によって為すのが一番易しい方法です。それでも心の深いレベルに対処するには、脳と心の動き方についての智慧と技術が四念処観を為す時に役立ちます。この智慧と技術を身につけるのが見聞持観の実践です。
一切事経による聞持観のつぎの段階は法次法向です。法次法向は阿羅漢に向かう最終段階です。この段階に行く前に、仏陀の智慧と技術をともなった四念処観を修します。
仏陀の智慧については本ホームページ 「仏陀の智慧と自然の神力」の項をご参照下さい。解脱に向かう技術、四念処観、四正断、擇法などについては、本ホームページとともに五巻の「仏陀に学脳と心」をご参照下さい。
聞と持
聞とは何を聞くのでしょうか。一切事経のテキストでは「正法」を聞くのだという。先ず「法」とは苦を寂滅させる心の動かし方と、脳と心の成り立ちについての智慧を表しています。これが正しいとはどういうことか。お釈迦様が説かれたことは、苦から脱出する道、すなわち解脱法です。正法をひと言で表すと、「解脱に向かう道と智慧」であると言えます。
このことを知るめに「見」と「聞」を実践します。
解脱に向かう道を歩んでいるグループを訪れて、お釈迦様が説かれた苦を滅する道についてその智慧と実践法を耳にするのです。
解脱に向かう智慧とは 何か。まず脳と心が世間からの情報に触れて老病死憂悲悩苦を生じる心の仕組みを知ります。二番目は老病死憂悲悩苦が生じないように脳と心の動きを変える、すなわち解脱に向かう道を知ります。この解脱に向かう智慧を聞き「持」すなわち理解し身につけます。
観
観とは何か。一切事経には「諸法の深義を観察し、甚深の妙義を観察する」とあります。
この諸法の深義、甚深の妙義を観察し解るようになること、これが「観」です。
このことを考察する前に一切事経に於ける、聞・持・観・法次法向が、盡智経に説かれた二十四段階の解脱システムとどの様に対応しているかを見ておきましょう。
盡智経に説かれた24の解脱の段階を見てみましょう、
一、 善知識に奉事す。
二、 往詣す。
三、 善法を聞く。
四、 耳界す。
五、 法義を観る。
六、 法を受持する。
七、 法を翫誦す。
八、 法忍を観る。
九、 信。
十、 正思惟。
十一、 正念正知。
十二、 護諸根。
十三、 護戒。
十四、 不悔。
十五、 歓悦。
十六、 喜。
十七、 止。
十八、 楽。
十九、 定。
二十、 見如実・知如眞。
二十一、厭。
二十二、無欲。
二十三、解脱。
二十四、盡智。中阿含経 盡智経より
見と聞は、
二、往詣す。三、善法を聞く。 四、耳界す。五、法義を観る。
に相当し、
持は、
六、法を受持する。七、法を翫誦す。
に相当します。
さて観は、まず 八、法忍を観る。
に相当しますが、諸法の深義、甚深の妙義を観察する段階はどの段階でしょうか。
八、法忍を観る。は心の動きに「忍」を観察することを示しています。このことは解脱に向かうステップの中で妙義とも言うべき大切な観察すべきテーマです。
(本ホームページ 「解脱に向かう」 の項 参照)
「法忍を観る」の次の段階は、九、信です。
この段階で完成した信によって、戒を護る信戒施を心の奥深くまで実践をするのです。信戒施の実践は四念処観と四正断・七覚支などによって為します。
十、正思惟。十一、正念正知。
の段階では忍の観察をともなって実践される戒を護る前段階です。
正思惟は、自然の神力(じねんのじんりき)を動かす際に必要なデータを蓄積し、正念正知はその目標を明確にします。
十二、護諸根。では四念処観を実践するときに必要な「擇法」の技術を身につけます。
正思惟、正念正知、護諸根をベースにして四念処観を為し、信戒施を実践してゆきます。
法次法向
解脱が進むと法次法向の階梯がやってきます。
法次法向は、二十一、厭。二十二、無欲。二十三、解脱。
の階梯に相当します。
法次法向については雑阿含経向法経に次のように説かれています。
佛比丘に告げたまはく。
「諦かに聽き善く思え。當に汝が爲に説くべし。
比丘、色に於て厭い欲を離れ滅盡に向かふ、
是を法次法向と名づく。受想行識も是の如し。
識に於て厭い欲を離れ滅盡に向かふ、
是を法次法向と名づく」と。すなわち法次法向とは、三つの心の動きを実践することです。
色(五蘊)に於て厭い
欲を離れ
滅盡に向かふ。これが法次法向です。
① 「色に於て厭い 」は、世間から脳と心に入ってきた情報に於いて厭う、すなわち掉慢無明を含む執着を捨離することを示し、
② 「欲を離れ」は、人類が動物として進化の過程でプログラムされた自己中心の我利を求める心の動き、すなわち動物の行動原理を離れることを示しており、
③ 「滅盡に向かふ」は人間の行動を規制し苦を生じる元になっている有結と愛(タンハー)を滅盡させます。
本ホーム頁「解脱に向かう」のなかに、阿羅漢であることを示すテキストがあります。
諸漏已に盡き、所作已に作し、諸の重擔を離れ、己利を逮得し、諸の有結を盡くし、正智にして心善く解脱す」
③「滅盡に向かふ」が完成すると「諸漏已に盡き」が成就し、
②「欲を離れ」が完成すると「所作已に作し」が成就し、
①「色に於て厭い 」が完成すると「諸の重擔を離れ」が成就し、ここから「己利を逮得し」すなわち施に向かう利他の心が完成します。
すなわち法次法向の三つの項目は解脱の完成に向かうことを示しており、このことが成就すれば、漏を滅してニルバーナに至ります。
八法から十六法へ
一切事経には、八法の各項目を実践しただけでは、在家の修行者として完成したとはいえないのだとあります。自分が成し遂げた苦から脱出する八法を、周囲の人達にも及ぼして、自分と同じように苦からの脱出を建立せよ、とあります。このことは阿羅漢の利他の心、「梵行已に立ち」を実践することを求めています。
難提経には、この部分を「己利を逮得する」こととし、布施の実践をなすことであると説かれています。
「己利を逮得す」は脳と心から自利に向かう動きが消えて、心が全て利他に向かう動きに変わったことを示しています。
難提経には五種の布施が説かれています。
① 解脱施、(一切事経の信・戒・施・聞・持・観の建立に相当)
② 捨施、(一切事経の法次法向の建立に相当)
③ 常熾然施、
④ 捨の平等惠施を楽い
⑤ 常に施の心を懐くべし
この五つです。
(詳細は本ホームページ 「阿羅漢に向かう」をご参照下さい。)
難提経の「施を為す」と一切事経の「八法から十六法を建立する」は究極の「梵行已に立ち」の姿を示していると思われませんか。
一切事経 まとめ
解脱への道は「信行・法行」と名付けられた階梯から始まります。
すなわち最初は仏陀への信の力によって戒を護って解脱に向かい、次は法すなわち智慧の力によって戒を護り解脱に向かいます。最初の信戒施は信行から始まり、聞持観に続く信戒施によって法行とそれに続く階梯を実践します。(当ホームページ ー阿含経を読む ー解脱へ向かう 参照)
解脱への道は、自分の心の至らぬ所に気がつき、これを直してゆくことから始まります。
戒の実践とは悪い心癖がなくなるように生活することです。
心を変える智慧と技術の第一歩は、自分が護るべき戒を知ることです。自分の「戒」を知る方法は、ひとつは「信」すなわち仏・法・僧により、もうひとつの方法は「施」の心によって世の事を行じようとすることです。さらに仏陀の智慧を身につけて奥深くの脳と心を変え、法次法向を為して、漏盡に向かいます。
一切事経では、この八法を周囲の人にも建立して十六法と為すことを求めており、在家であっても阿羅漢に向かう「梵行已に立ち」を実践すべきことを説いています。
Copyright © 2012-2015 Web Design Thinknet,Japan Ltd All Rights Reserved